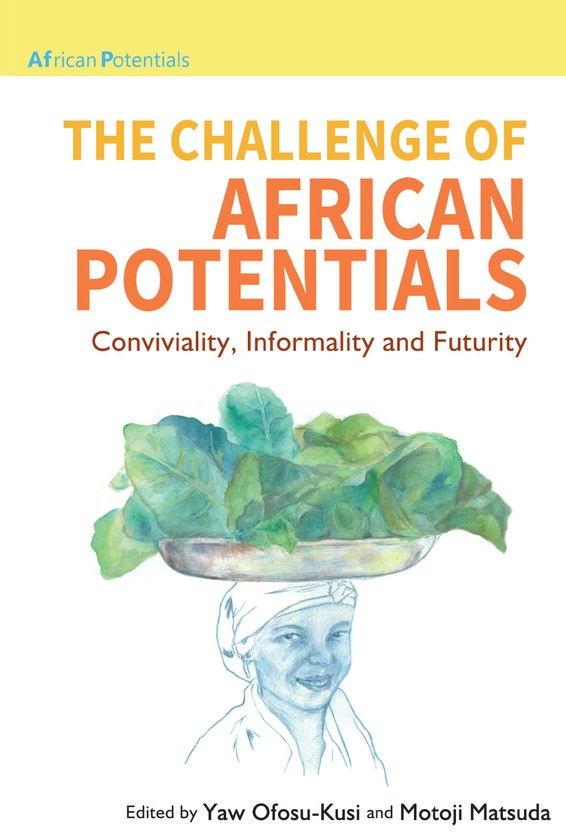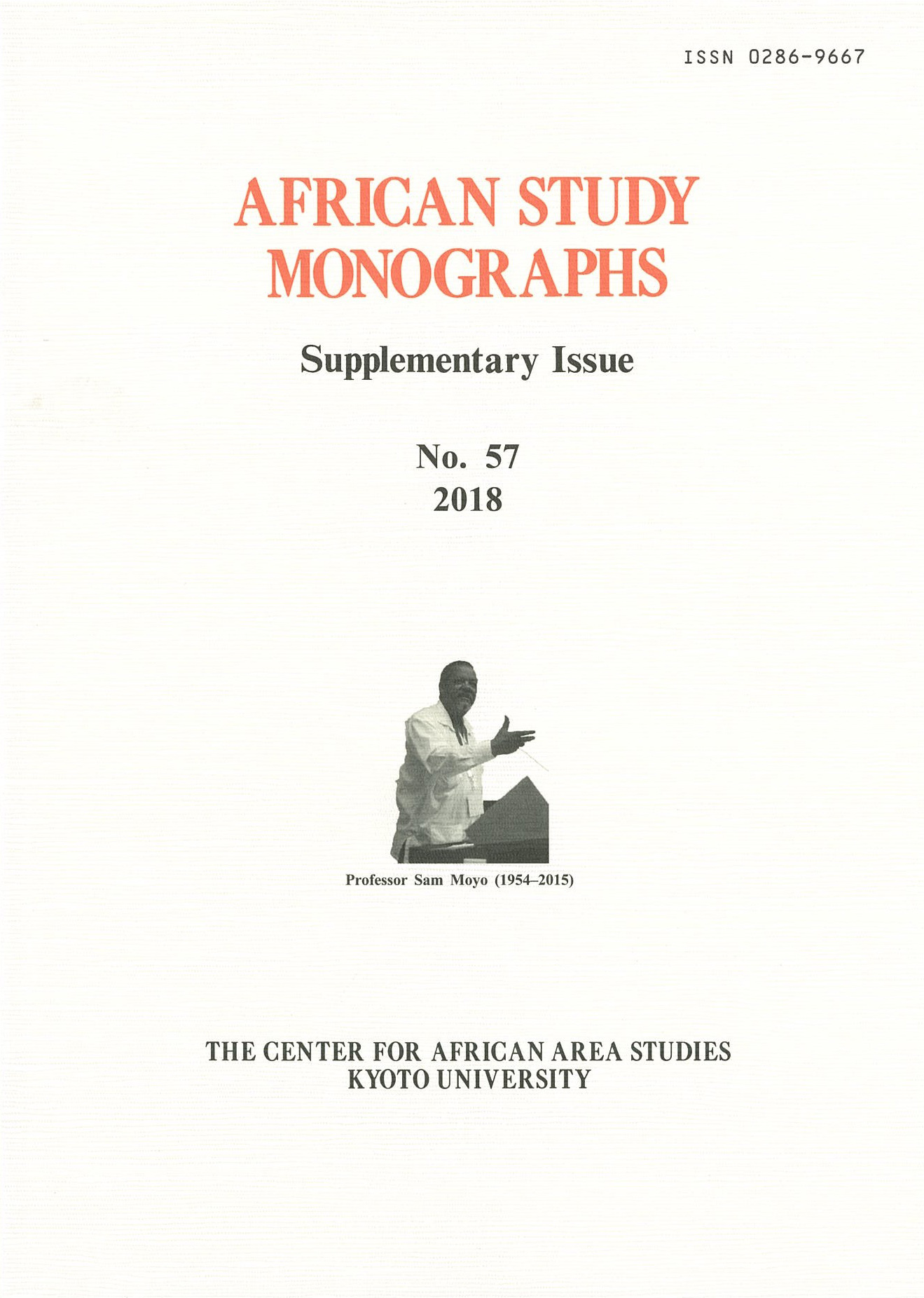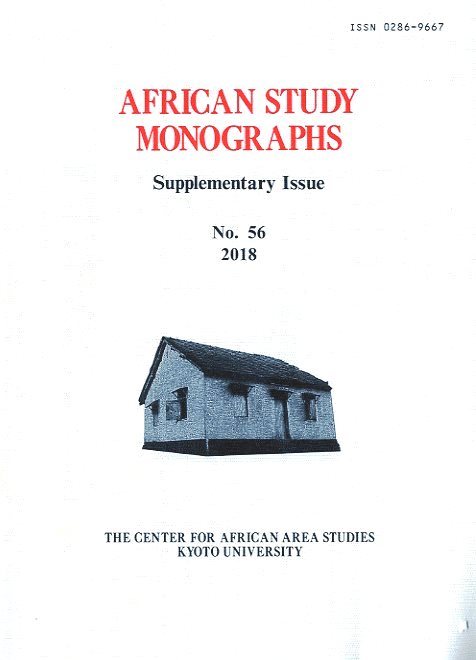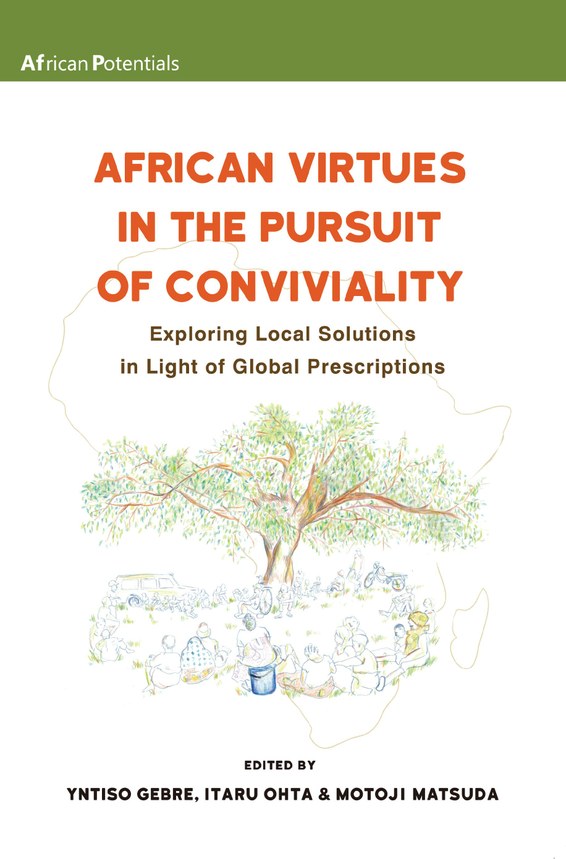[海外出張報告] 沓掛沙弥香(言語・文学班)タンザニア 海外出張期間:2017年2月2日~3月1日
「タンザニアにおける言語格差の表出:学校教育と言語」
沓掛 沙弥香
(派遣先国:タンザニア/海外出張期間:2017年2月2日~3月1日)
タンザニアは、スワヒリ語に国家語(national language)と公用語(official language)としての地位を与えています。その一方で、英語も公用語として使用されています。しかし、同様に「公用語」としての地位が与えられていても、スワヒリ語と英語の間には、社会的役割の差が存在しています。
タンザニアでは、小学校教育の教授用言語はスワヒリ語ですが、中学校以上の教育では教授用言語が英語に変わります。中学校以上の教育で英語が使用され続けていることは、英語がタンザニアにおける社会的高位の言語として君臨し続ける要因となっています。また、独立当初社会主義政策を掲げていたタンザニアでしたが、1986年に構造調整政策を受け入れ、1990年代に教育の自由化を行うと、英語を教授用言語とする私立小学校が急増しました。児童数の増加に対応しきれず公立小学校の「教育の質」の低下が著しい一方で、私立小学校が有利な教育環境を有している状況が、それらの学校が使用している言語が英語であるという状況と相まって、英語の社会的価値をさらに高める結果となりました。
このような状況があったものの、スワヒリ語という一つの言語で理解し合えることは、タンザニアの人々の中に「Umoja(unity, 統合)」の意識を形成しており、他のアフリカ諸国に見られるような言語格差による不平等性は、タンザニアではあまり深刻な問題として社会に認識されていない状況でした。しかし、私の近年の調査では、このような状況に変化が表れてきていることが確認されています。これまで、タンザニアにおけるスワヒリ語と英語の相克状況というのは、英語を教授用言語とする中学校以上の教育への進学率が高く、英語を教授用言語とする私立小学校へのアクセスも可能な都市部における研究課題となっていました。ところが、私が2015年、2016年に行ったタンザニア南部の地方都市および農村部においても、人々は英語の習得に積極的な態度を示しており、英語へのアクセス権において、大きな格差が存在していることを問題化していたのです。結果として、多くの人々の発話の中に、英語へのアクセスや教育機会の格差に伴う「階層(tabaka)」や「差別(ubaguzi)」のような単語が散見されました。このような変化は、独立以来人々の間で強く信じられてきた国家統合の意識にも影響を及ぼすかも知れない重要な変化です。私のこれまでの研究では、地方都市における英語へのアクセス権に絞って研究していましたが、今回の渡航では、比較対象としてもっとも恵まれた教育環境にアクセス可能な地域と考えられるタンザニアの首座都市ダルエスサラームにおいて調査を行ってきました。
調査では、ダルエスサラーム州内の2つの私立小学校(英語を教授用言語とする)において聞き取り調査と参与観察を行い、また、英語による教育を受けた方や、自分の子どもに英語による教育を受けさせている方4人に、英語に関するインタビュー調査を行いました。

H小学校(私立)の歴史の授業の様子(ダルエスサラーム)

P小学校の英語の授業の様子(ダルエスサラーム)

子どもたちは一人一人、教科書、ノートを持っています。筆箱や水筒も。また、イスも一人に一脚、机は2人で一台ですが、十分なスペースが確保されています。
タンザニア南部における調査では、基本的に人々が公立小学校にしかアクセスできない環境の中で、英語を教授用言語とする学校で教育を受けることができる人との格差が問題になっていました。実際、農村部には私立小学校自体が存在せず、あったとしても、農業従事者にとって私立学校で子どもたちを学ばせるための学費を得ることはほとんど不可能な状況ですから、当然の状況と言えます。(例えば今回調査した私立小学校の1つの学費は1,500,000Tsh/年、日本円で約74,000円/年でした。タンザニアの公立学校の教師の給料が3,000,000~5,640,000Tsh/年、日本円で144,000~280,000円/年であることを考えると、非常に高額です。)しかし今回の調査では、英語による教育の中にも支払う金額による格差があることがわかりました。また、私立小学校の中にはわずかながらスワヒリ語を教授用言語にしている学校も存在し、それらの学校の中には優秀な成績を収めている学校もありますが、全体の成績で見た場合、上位の学校は全て英語を教授用言語とする私立小学校という状況も確認されました。そのため、社会的に高位の言語である英語へのアクセスを求める気持からも、「せっかくお金を払うなら、英語を教授用言語とする学校へ」となってしまっている状況です。
タンザニアの小学校教育レベルでは、英語で教えるのか、スワヒリ語で教えるのかという言語の問題以前に、スワヒリ語で教えている公立小学校の教育がおおよそ壊滅的な状況であるという問題が存在しています。たとえば、私が調査を行った村の小学校では、スワヒリ語の授業中、そのクラスに教科書が一冊しか存在していませんでした。「教師が教科書に載っているスワヒリ語の題材を音読し、その文章に関する練習問題を板書し、生徒がそれをノートに写し、解く」という状況でした。これでは「読解力」は得られません。この学校の2015年の小学校修了試験の成績は、全国16096校の小学校のうち14124位でした。農村部で子どもたちがアクセスできる学校のほとんどが、このような状況にある公立小学校だけなのです。

農村部のM小学校の様子。子どもたちの中には、ノートやペンを持っていない子もいます。
一方で、都市部では一人に一つのイス、机、教科書が用意され、良い給料を支払われる教師が熱意を持って教える私立小学校がたくさんあり、お金さえあれば、そのような小学校にアクセスすることができます。このような格差状況が、英語による教育とスワヒリ語による教育の格差という形で人々に認識され、「英語=教育」という意識を強化している状況があることが、今回のダルエスサラームでの調査から改めて確認されました。
[海外出張報告] 桐越 仁美(開発・生業班)ニジェール、ガーナ 海外出張期間:2017年3月6日~21日
「西アフリカのコーラナッツ交易を支える連携と信頼の商業ネットワーク」
桐越 仁美
(派遣先国:ニジェール、ガーナ/海外出張期間:2017年3月6日~21日)
西アフリカでは、輸入された海外製品が港で大型トレーラーに積み込まれ、次々に内陸部へと運ばれています。沿岸部から内陸部に輸送されていく海外製品のなかには日本や中国などから輸入された中古バイクや中古自転車、中古の家電製品なども多く含まれ、近年では内陸部におけるこれらの輸入品の需要が高まっています。海外製品の内陸部への輸送を支えているのが、西アフリカの歴史的商業ネットワークです。西アフリカでは、紀元前1000年から北アフリカとのあいだでトランス・サハラ交易が発展しました。トランス・サハラ交易やその後に発展した大西洋貿易は西アフリカ各地をむすびつけ、異なる生態ゾーンとのつながりを構築しました。
西アフリカの歴史的交易のなかでは、コーラナッツという商品が重要な交易品とされてきました。コーラナッツとはアオイ科コラノキ属コラノキ (Cola nitida) の種子です。コーラナッツはおもに西アフリカのサバンナ地帯やサヘル地帯といった内陸乾燥地域において、古くから嗜好品として消費されてきました。コーラナッツの特徴として、鮮度を維持したまま輸送される点、消費地は内陸乾燥地域であるのに対して生産地は南部の森林地帯に限定される点の2点があげられます。このような特徴から、鮮度を維持しつつも、ときには2,000km以上の道のりを輸送しなければならず、19世紀以前には輸送に多大な労力と財力を必要としました。交易を通じてコーラナッツの商品価値は高まり、内陸乾燥地域においては富と権力の象徴として儀礼的・社会的に高い価値が与えられました。コーラナッツは現在でも内陸乾燥地域で日常的に消費されており、森林地帯から内陸乾燥地域に向けて大量に輸送されています。私の研究は、現在のコーラナッツ交易がどのような商業ネットワークのもとに成立しているのかに着目しています。
今回の渡航では、コーラナッツの生産地であるガーナ南部と消費地であるニジェール南部の2ヵ所で調査を実施しました。ニジェールでは首都ニアメの市場グラン・マルシェと資材市場カタコの2エリアに位置するコーラナッツの配荷場を対象に調査をしました。消費地であるニジェールの情勢悪化によって、2013年以降、私の調査は生産地であるガーナに限られていたのですが、今回は初めて消費地を対象とした調査をおこないました。おもにコーラナッツの価格や配荷場のシステムについて調査を実施し、過去にガーナで調査したコーラナッツの輸送システムとの照合をおこないました。ガーナでは、輸送上の取引に関する調査とあわせて、コーラナッツ交易に関わりのある若者たちのこれまでのライフコースや今後の展望についての聞き取り調査も実施しました。調査対象の若者たちのほとんどは、ガーナ国内外の内陸乾燥地域からガーナ南部に移住した人びとであり、同じく内陸乾燥地域を出身とする商人のもとで修行を積んでいます。
これまでのガーナにおける調査からは、コーラナッツの消費地への輸送の行程において掛売りや委託販売といった手法が採用されており、商人間の連携や信頼が重要であることが明らかになっていました。今回は生産地であるガーナに限らず、消費地であるニジェールでも首都から地方への輸送の行程で掛売りが採用されていることが確認できました。また、ガーナにおける若者たちへの聞き取り調査からは、商人間の連携や信頼のうえに成りたつコーラナッツ交易に関わることへの誇りを垣間見ることができました。コーラナッツ交易は歴史ある商売であり、長い修行期間を必要としますが、多くの若者がコーラナッツ交易に関わることに喜びを感じており、修行を通じて次のステップを模索している状況にありました。また聞き取り調査のなかで、西アフリカの交易には大きく分けて2つのタイプがあり、コーラナッツや塩などの歴史的な交易と、海外製品などを扱う新しい交易に分けられることが明らかになりました。さらにこれら2つの交易のあいだでは異なる商慣行がみられます。しかし、この2つの交易が互いに影響しあわないわけではなく、若者たちはこの2つの交易を柔軟に行き来することで、みずからの人生の指針を得ようとしていました。今後は、これら2つの交易の違いについて調査・分析し、若者の人生設計や歴史的商業ネットワークの新しい交易への活用について考察していきたいと考えています。

ニアメのコーラナッツ配荷場の内部

ガーナのコーラナッツ商人たち
[海外出張報告] 岩井 雪乃(環境・生態班)タンザニア 海外出張期間:2017年2月8日〜13日
「アフリカゾウを追い払う:実践と困難」
岩井 雪乃
(派遣先国:タンザニア/海外出張期間:2017年2月8日〜13日)
タンザニア北部地域では、2000年代に入ってからアフリカゾウが農作物をあらす害獣となっている。かつてはゾウは保護区内にいたが、村の中まで畑の作物を食べに入ってくるようになってしまい、時には人が殺される事件も起きている。村びとたちは、自分の生活と生命を守るためにゾウを追い払い、保護区に戻そうと努力するが、10トンもある巨大な生物に立ち向かうのは命がけである。そして、それが1頭のみならず多いときには200頭もの群れで押し寄せて来ることもある。このような状況に人びとはどう対処しているのだろうか。

家の前で平然と木を食べるゾウ
本調査では、筆者が1990年代から調査を続けているセレンゲティ国立公園の西側に隣接する村落で、村びとによるゾウ追い払いをつぶさに観察する機会を得たので報告したい。
2月半ばのその日は、前日に久しぶりに雨が降った日だった。午後4時ごろ、村びととともに、村と保護区の境界に設置しているワイヤーフェンスを見回っていると、ゾウの群れ(6頭)を発見した。ゾウは、まだワイヤーの外(保護区側)にいたが、しきりにワイヤーを嗅ぎ回っているので、今にもポールを倒して入ってきそうだった。

村の中に入っているゾウ
近所の若者たちに連絡がいき、すぐさま10名ほどが集まった。口笛、ブブゼラ、バロティ(銃声に似た音がでる爆竹機)、犬、弓矢など、それぞれに持っている道具を駆使してゾウを脅かし、ワイヤーから離れた保護区の方へ追いやった。解散した時には夜8時になっており、家に着いたのは10時ごろになっていた。

若者たちの追い払いチーム
ところが翌朝、ゾウはワイヤーの切れ目を見つけ出し、村の中に入っていた。朝8時から再び追い払いが始まった。15名が集まって出動。しかし、3時間追い払っても、ゾウは出ていってくれない。脅かされて逃げてワイヤーにぶつかると、また村の方に戻ってきてしまい、なかなかワイヤーの切れ目に行ってくれない。そのうちに、群れが分かれて2頭と4頭になってしまい、追い払う人数が足りなくなってしまった。近隣地区からも応援をよび、さらに人数を増やして右往左往すること10時間。夕方6時になって、ようやく切れ目から保護区へ出ていった。
帰路につく時、若者たちは満身創痍だった。ゾウとともに数十キロを走り回った結果、ねんざして杖をつくもの、木の根を踏み抜いてびっこを引くもの、爆竹機でやけどしたもの・・・。そして、全員が疲労困憊してお腹をすかせていた。
わたしはこの翌日に村を後にしたが、その日の晩にもまたゾウ群が来て、若者たちは一晩中追い払いをしたそうだ。彼らは、寝る間もなく生計のために労働をしている暇もない。これでは彼らの生活が成り立たず、追い払いを続けることもできなくなり、ゾウに対処できなくなってしまうことが懸念される。そうなった時、人びとは自らの生活をどうやって成り立たせるだろうか。ある村びとは、「畑の作物をゾウに食べられてしまうなら、狩猟をするしかないじゃないか」と怒りをあらわにしていた。
セレンゲティ地域の人びとにゾウを保護することを強いているのは、タンザニア政府であり、観光業者であり、ゾウを見たい観光客であり、自然保護を求める先進国のわれわれである。村びとが試みている「ゾウと共存するための追い払い」をどう支援できるのか。わたしはこれまでに、32kmのワイヤーフェンスを設置するプロジェクトをおこなってきた。現在、次なる展開を模索しているところである。
[海外出張報告] モハメド・オマル・アブディン(対立・共生班)スーダン 海外出張期間:2017年1月23日~2月23日
「スーダンにおけるFGM/C正当化の論理とその変容」
モハメド・オマル・アブディン
(派遣先国:スーダン/海外出張期間:2017年1月23日~2月23日)
スーダンにおけるFGM/Cの擁護派と反対派間の対立の現状と、双方が自らの主張を正当化するためにどのような論理を用いているのかを解明することを目的として本調査を行った。とくに、FGM/Cの問題が、政治論争のトピックとして表れている現状に注目しながら、FGM/C正当化の論理とその変容を明らかにしていきたいと考えている。
現地調査は、スーダンのハルツームにおいて実施した。まず、厚生省、内閣管轄下の国立子供福祉協議会(National Council of Child Welfare)、国会(National Assembly)におもむき、関連資料を収集した。また、ハルツーム大学社会開発研究所、アハファード大学ジェンダー研究所の担当者と面会してインタビューをおこない、図書館では資料を収集した。そして、青年男性(20代から30代)グループへのインタビューを実施し、また、複数の男性を集めてディスカッションを行うことも試みた。
今回の調査により、スーダンにおいては、FGM/Cの正当化をめぐって従来の成女儀礼としてではなく宗教教義として、認識され始めていることが明らかになってきた。すなわち、擁護者は、グローバルな反対運動の影響が強くなるなか、「伝統儀礼」として正当化することが困難になっていることから、別の論理を新たにつくるという動きがみとめられた。これに対して反対派は、FGM/Cは宗教との関連が薄いことを主張するという、消極的な対応にとどまっている。また、行政は、撲滅運動に前向きであり、キャンペーンなどを実施している一方、立法面では、FGM/Cの禁止法案を否決するなど、立法と行政の間では不整合がみられ、FGM/Cをめぐる現状は複雑化している。
今回は主として、擁護派と反対派がみずからの主張を正当化する論理がいかなるものであるかを調査してきたが、今後は、双方の主張がどのように一般の人びとに浸透しているのかを調査していく。また、男性グループのディスカッションを組織して感じたのは、公の場におけるこの問題への人々の発言と本音との乖離である。この事実は、FGM/Cについて語ることが、依然としてタブーであることを裏付けるものであるが、調査の方法を慎重に選びながら進めなければ、現状を正しく理解することは困難である。今後も、文献調査とインタビューを並行しながら調査をおこなっていくが、その際に、宗教家や医師など、FGM/Cに関連して人々によく知られている具体的な個人の活動とその人に対する人々の意見に注目しながら調査をすすめていきたい。
[海外出張報告] 塩田 勝彦(言語・文学班) ナイジェリア 海外出張期間:2017年2月24日~3月13日
「『ジュジュ』を読む:言語学・文学資料としてのヨルバ語ポピュラー音楽の分析」
塩田 勝彦
(派遣先国:ナイジェリア/海外出張期間:2017年2月24日~3月13日)
20世紀初頭、蓄音機の普及とともに西アフリカでも商業録音が始まり、数多くの現地音楽が録音され、レコードとして発売されるようになりました。マスメディアと結びつくことによって、現地音楽はその形を整え、西アフリカにおけるポピュラー音楽が成立したのです。
この時期はまた、ギニア湾岸の港湾都市を中心に都市化が進み、経済の発展とともに外国文化も流入し、社会や価値観が急速に変動していく時代でもありました。
西アフリカのポピュラー音楽は、変わりゆく社会とともに成長し、社会を映す鏡として、またある時は社会に影響を与える言論の道具として機能してきました。
西アフリカには現地語で出版された書籍や新聞、雑誌などもありますが、庶民にとってレコードや街角で流れる流行り歌は、活字よりずっと身近なものだったと考えるべきでしょう。
アフリカ出身者が多いカリブ海のトリニダード・トバゴでは、現地のポピュラー音楽であるカリプソが、しばしば「プアマンズ・ニューズペーパー」と呼ばれていました。ポピュラー音楽には時事を伝える瓦版としての機能もあったのです。
アフリカにおけるポピュラー音楽は1970年ごろから熱心に研究されるようになり、いくつかの音楽ジャンルに関しては、その民族音楽学的、および社会史的側面がかなり明らかにされてきています。
ナイジェリアのラゴスは、そのようなポピュラー音楽が早くから栄えた都市のひとつです。ラゴスには古くから多くの民族、文化が流入していますが、基本的にはヨルバ人の町です。
ヨルバ民族は、お互いに系統を同じくしながら異なる歴史を重ねた都市国家群から構成されており、19世紀は相争う戦国の時代でした。言語もそれぞれが異なる方言を持ち、標準語が整備されたのも19世紀半ばになってからです。その後イギリスの支配下に置かれて社会は安定し、同じ民族としてのアイデンティティを強めていきます。
20世紀には「ヨルバ」としての民族意識も高まり、ナイジェリアの独立へ向けて大きな役割を果たすことになるのですが、その過程を様々に記録し、民衆の声を代弁し、その心情を描写してきたのがヨルバのポピュラー音楽でした。
ヨルバのポピュラー音楽は、民衆の歴史観をヨルバ語で記録し、詩的言語の豊富なバリエーションを提示し、民衆レベルでの言語推移の記録を留めた、貴重かつ豊かな資料であると言えるでしょう。
今回の調査では、音源を入手できたヨルバのポピュラー音楽のうち、録音最初期の1920年代から独立後10年ほど、すなわち1960年代末までのものを選び、歌詞の聞き取りと翻訳をナイジェリア人研究者との共同で行いました。
作業はエキティ州、アド・エキティ市のエキティ州立大学(EKSU)文学部、言語学・ナイジェリア言語学科のM.A.アビオドゥン教授、O.アラム教授、および大学院生数名の協力で順調に進み、約40曲のデータが収集できました。
本格的な資料の分析はこれからですが、整理の過程で以下のような点に気付きました。
1)ヨルバ語には「深いヨルバ語(ìjinlè̩e̩ Yorùbá)」と呼ばれる、通常の口語とは異なる語彙と文法からなる芸術的変種が存在し、もっぱら詩の創作に用いられていますが、この「深いヨルバ語」が最初期の録音からすでにポピュラー音楽の中に取り入れられていたようです。
初期のヨルバ語ポピュラー音楽は、その演奏者が必ずしもヨルバ人というわけではなく、片言のヨルバ語を許容する風潮も認められていたのですが、歌詞そのものには早くから高度な芸術表現が用いられており、詩作の伝統との関連が注目されます。
2)前述のように、ヨルバ語は19世紀から標準化が進められており、商業録音が開始された20世紀初頭には、少なくとも都市部のリンガフランカは標準ヨルバ語になっていたと考えられています。録音音源は全時代を通してほぼ標準語で歌われていますが、ところどころに方言が組み込まれています。興味深いのは、初期のものより、標準語がより隅々まで普及した独立後の60年代のものに方言要素が多くみられるということです。圧迫された方言が地方出身者の郷愁や連帯感の象徴になりつつある、その過程の表出と考えられるかもしれません。
3)ヨルバ文化は、北部から流入してきたサヘル文化とのつながりが深いイスラム文化圏と、南部の港から流入してきた西洋文化とのつながりが深いキリスト教文化圏の二つに大別でき、その両者がさまざまな度合いで伝統宗教・文化の影響を受けています。ポピュラー音楽もイスラム文化圏に属するもの、キリスト教文化圏に属するものに分けることができますが、イスラム文化圏の音楽が楽器編成、歌詞の表現などにおいてヨルバの伝統的な(少なくとも、その時代にはそう思われていた)様式にこだわる一方、キリスト教文化圏の音楽は、比較的新しい外来要素(ラテン音楽のリズムや西洋楽器など)を抵抗なく取り入れ、歌詞にも個人的な感情表現が見られるようです。保守的なイスラム文化圏と進取の気性に富むキリスト教文化圏というヨルバランドにおけるステレオタイプは、ポピュラー音楽においても(少なくとも、表面的には)そのまま支持されているように見えます。
今後はこの資料を整理し、言語・文学および歴史的観点から注釈をつけ、保管・公開へ向けた作業を続けていく予定です。

イバダンのCDショップ。この店はヨルバ音楽だけを扱っている。

調査に協力していただいたA・アビオドゥン教授。エキティ州立大学にて。
[海外出張報告] 味志 優(国家・市民班)タンザニア 海外出張期間:2017年2月27日~3月17日
「タンザニアにおける小規模の汚職をめぐる認識のあり方:論と実生活との狭間で」
味志 優
(派遣先国:タンザニア/海外出張期間:2017年2月27日~3月17日)
今回、私はタンザニアのダルエスサラームと北西部のバリアディという地で、汚職や国家の法に対する人々の認識のあり方に関して予備調査を行いました。
周知の通り、特に植民地支配からの独立以来、汚職はアフリカ諸国にとって大変関わりの深いテーマであり続けてきました。近年「グッド・ガバナンス」が広く推進されていることからも分かるように、とりわけ経済開発との関わりにおいて、依然として汚職は非常に問題視されています。
この汚職というテーマに対して、私は調査地の人々の認識のあり方という側面からアプローチすることを試みています。つまり、汚職または法を犯すという行為に対して、我々ないし先進国の人々は悪いイメージ、あるいは日常生活から離れたイメージを瞬間的に抱きますが、調査地の人々はそれとは異なる形で汚職を認識しているのではないか、という問いを探求しています。仮にこうした異なる形で汚職が認識されているならば、開発の議論において「汚職の状況の改善」をただただ要求し、あるいはそのための制度を構築したとしても、人々の実践においては本来の意図通りに結果が生じない可能性があります。また、異なる形で汚職が認識される可能性があるにもかかわらず、特定の認識のあり方を前提にしてアフリカを「腐敗した」国家として断罪することの危うさも提起されます。こうした意味でも、汚職というテーマを認識のあり方という面から考察することは重要であると考えています。
このような背景を踏まえて、今回の予備調査では、ダルエスサラームおよびバリアディにおいて簡単な聞き取り調査を行いました。ただし、汚職といってもその種類は多岐にわたります。最も大きく分類すれば、主に大物の政治家が関与するような、多額の資金が関わる大規模な汚職(“grand corruption” としばしば呼ばれます)と、より下位の行政官や警察官が関わるような小規模な汚職(“petty corruption”)があります。今回は、特に人々の日常生活において身近な、後者の小規模な汚職に関する人々の認識のあり方を探りました。
端的に言えば今回の調査において痛感したことは、非難される対象としての「汚職」という概念が共有されている一方で、人々の生活空間における具体的な汚職行為に関しては多様な認識がなされている、ということでした。さらに言えば、人々は大規模な汚職に関しては非常に嫌悪感を抱き非難する傾向にあるのですが、小規模な汚職に関しては、さらに細分化される事例の状況に応じて、あるいは各個人の経験に応じて、その認識のあり方や抱く感情に差異があります。他方でそれと同時に、近年のグッド・ガバナンス論の興隆を背景に、概念として汚職が非難されるべき対象であるという理解もあり、こうした概念としての論と実生活の中の具体的な行為の認識との狭間に人々がいるように思えました。
実際の汚職行為に対する多様な認識のあり方について、いくつか例を挙げます。今回聞き取りを行った人々によれば、彼らが日常生活において最も頻繁に遭遇する汚職の場面は、自動車を取り締まる警察官が運転手に賄賂を要求する、というものです。そこで、警察官による賄賂の要求、という要素だけを固定しながら架空の事例をいくつか用意して、それに対する人々の意見を聞き取りました。まずは、仮に自分が車を運転していて、シートベルトを締めていなかったことが警察官に見つかったという事例です。罰金として30,000シリング(日本円で約1500円)を国家に支払う代わりに、その警察官に対して個人的に10,000シリング払えば見逃してもらえる、と警察官から提案された場合にどうするか、と聞いた際には、ほとんど全ての人がその賄賂を支払う、と回答しました。また、この事例に関しては、賄賂を支払う動機やそれに対する感情はおおよそ内容が類似していました。それは「皆がやっているのだから自分だけやらない理由はない」というものです。つまり、賄賂を支払うことが、一般的にメディア等で非難される「汚職」に与する行為であると理解していながらも、自分にとってペイするものであり、かつ周囲でも頻繁に行われているものであるから、多少の罪悪感は感じながらも半ば当然のものとして支払う、というものです。
他方で、この事例を提示した際には、回答者が多少の怒りを示しながら、自身から補足を始めることも少なくありませんでした。それは「警察官側は何かしら理由を探してでも賄賂を要求してくる」というものです。つまり、シートベルトの締め忘れや交通違反といった外部から判別できる違反がなくとも、警察官が車を脇に停めさせることは少なくなく、その場合警察官は免許証や車の保険の有効期限をまず確認し、そこにも問題がなければ、消化器や三角表示板の搭載を確認してまで違反を探し出し賄賂を要求しようとする、と不満を口にする回答者が多くいました。あるいは回答者によっては、警察官は最後には車を揺らして車からガソリンが滴るかどうか確認する、とあきれて笑いながら話した者もいました。また、このようにして警察官によって「あぶり出された」違反に対して要求される賄賂に対しては、人々はよりネガティブな感情を抱いていました。さらにその中でも、免許証の不携帯や車の保険の期限切れに対して要求される賄賂に関しては、多少は人々が納得していることが感じられましたが、特に消化器や三角表示板の搭載に対して要求される賄賂に対しては、明らかにネガティブな感情が読み取れました。
それに加えて、賄賂によって自らが得をするような事例に関しても意見を聞きました。自分と共にダルエスサラームに上京した友人が警察官に就職したと仮定して、その友人が、賄賂で得た金で自分にビールを奢ると提案した時にどうするか、という事例です。これに関しては回答者によって大きく差異が見られました。すなわち、迷わず奢ってもらう、あるいはさらに多くの賄賂を得て、より多くのビールを奢るよう助言する、と答える回答者もいれば、賄賂を得ることをやめるよう勧めるとの回答もありました。前者の回答に関しては、賄賂を獲得できる立場にあるのにそれを行わない方が愚かである(“It’s stupid not to do it”)という理由を説明する回答者もいました。それに対して後者の回答に関して理由を聞いたところ、「賄賂の要求を続けた結果、偶然自分に近しい人物から賄賂を受け取った際に人間関係が崩壊するかもしれない」や「果てしなく続く欲望に打ち克たなければならない」といった回答があり、法を守ることの重要性自体は指摘されなかったのが印象的でした。
こうした回答を踏まえた上で、人々の認識のあり方に対していかなる解釈を行うべきか、という点は今後さらなる課題として設定していますが、今回の調査を通じて以下の点ははっきりと実感することができました。つまり、一口に「汚職」と分類される行為に対しても、少なくとも私が今回調査を行なった人々の間では、文脈に応じて多様な認識がなされています。時には、ある種の非公式の制度とも言えるほど当然のように与するような行為であり、時には「被害」を受けたと強い憤りを感じるような行為であり、あるいは友人を通じて自らに恩恵をもたらす行為でもあり、それに遭遇することで自らの倫理や認識のあり方を確かめる機会を与えるものでもあります。しかし同時に、そうした行為は一般的に非難されている「汚職」に分類されるものであると、皆が理解していることにも着目しなければなりません。私が汚職の話題を出せば、多くの回答者は少し顔をしかめながら汚職が国にはびこっていることを指摘していました(“Corruption is everywhere”)。つまり人々は、一方で個々の行為に対しては、その文脈に応じて多様な認識や感情を抱いていますが、同時に他方で、グローバルに展開されている、ある種概念的に「汚職」を非難するような言説に触れ、それを内面化せざるをえない状況にあります。また、現政権は汚職に対してかなり厳格な態度を取っており、警察官も以前ほど賄賂を要求できなくなっている、との声も多数耳にしました。賄賂を要求している姿を撮影した動画がインターネット上で共有され、最終的にはその警察官が公的な処分を受けた、という事例も出てきています。
今後は、上記のような多様な認識のあり方に対する解釈の仕方を模索するとともに、このようなある種の「狭間」とも解釈できる状況下で、調査地の人々の認識のあり方がどのように変化するのか(しないのか)という点にも焦点を当てて調査を進めていく予定です。汚職を非難する言説も、概念として汚職は悪であるという人々の認識も、もはや不可逆な流れの上にあると考えています。そうした中で、実生活の中に具体的に位置付けられるような、汚職行為や法の違反・遵守に対する人々の認識のあり方がいかなる動態性を持っているのかを観察していく予定です。

調査地近くのミッション系の私立中学校(休み時間)。厳格な教育が行われているが、その卒業生であっても、個別の汚職行為に対する解釈は他のインフォーマントと大差なかった。

ダルエスサラームのバー。出産を祝う催しが開かれていた。共に飲食・飲酒をすることで
初めて汚職行為に関して語ってくれたインフォーマントもいた。
[海外出張報告] 西﨑 伸子(環境・生態班)南アフリカ、ケープタウン 海外出張期間:2017年3月4日~3月8日
「ワークショップ『アフリカにおける参加型観光』への参加報告」
西﨑 伸子
(派遣先国:南アフリカ、ケープタウン/海外出張期間:2017年3月4日~3月8日)
南アフリカ・ケープタウンで開催されたワークショップ「アフリカにおける参加型観光」に、本プロジェクトとかかわりの深い日本人研究者とともに参加し、研究発表をおこないました。最初に主催者からワークショップの趣旨が説明されました。会場である!khuwa tuuで働くスタッフが参加していたため、アカデミックな事例報告だけでなく、アフリカ観光の特徴や課題を参加者全員が共有できるように、議論のポイントが3点示されました。一つ目は観光産業に地元住民がどのぐらい参加するべきなのか、二つ目は、観光から受け取る地域住民の便益とは何か、三つ目は観光がもたらす負の影響は何か、です。
わたしは、「エチオピアの民族観光」について報告しました。とくに近年、外国人観光客数が著しく増えているエチオピア西南部の民族文化観光の実態を報告し、ホスト側と観光客の「出会い」と「まなざし」によって、若者層を中心に観光業へ参入するアクターが増えていること、アクターの多様化によって地域の観光資源が豊富になっていること、それによって地域住民の参加や経済的収入を得る機会がつくられていることを説明しました。観光業が新しい産業として地域にはいってきていると同時に、開発にともなう土地収奪によって、産業として不安定な観光業に農牧民が依存せざるをえない状況となっていることを強調しました。

ワークショップの様子(松浦直樹氏撮影)
タンザニア、ケニア、ボツワナ、ガボンの自然観光と民族文化観光の事例報告に加えて、!khuwa tuuの説明をスタッフからしていただきました。会場となった施設は、NGOが所有・運営しており、ブッシュマン観光を観光客に提供したり、そのためにスタッフにトレーニングをおこなったりしています。ミーテンィグルームだけでなく、とても清潔でおしゃれな宿泊施設やレストランを併設しています。最後の総合討論では、コメンテーターを含めて、コミュニティの観光のかかわりなどについて活発な議論がおこなわれました。

ブッシュマン観光のトレーニングについて
[海外出張報告] 西 真如(開発・生業班)ウガンダ 海外出張期間:2016年12月31日〜2017年1月7日
「うなづき症候群と生きる村」
西 真如
(派遣先国:ウガンダ/海外出張期間:2016年12月31日〜2017年1月7日)
今夜も野焼きをするけど、一緒に来ないか――そう声をかけてくれたお父さんについて小屋を出た。暗い畑地を通りぬけてゆく道すがら、夜のほうが風が吹かないので火を入れるには都合が良いのだと説明してくれる。10分ほども歩いただろうか、今日はここからあの奥の方まで焼くのだと言って藪に火をつけた。燃え広がろうとする火を、一緒に来た助手の若者が木の枝で叩いて鎮圧しつつ、帯状に焼いていく手際の良さに驚かせられる(写真1)。この村の人たちは、こうして毎年、同じように火入れを繰り返してきたのだろう。そんなことを思いながら野焼きの作業を見ていると、この地域でおこなわれた凄惨な暴力が収束してから、まだ10年も経たないということが、信じ難く思われる。

写真1:野焼きの火
ここで「お父さん」と呼ぶのは、ウガンダ北部のアチワ川流域での調査でお世話になった世帯のあるじである。ウガンダ北部では1980年代から、「神の抵抗軍」を名のる反乱軍とウガンダ政府軍とが衝突する中で、虐殺や誘拐、略奪が横行した。暴力がおおむね収束し、アチョリの人々が暮らす村に日常生活が戻り始めたのは2007年以降のことであるが、ちょうどその頃からアチワ川流域では、「うなづき症候群」(Nodding Syndrome) と呼ばれる病気の流行がみられるようになった。患者の多くは10 代までに発症し、頻繁なてんかん症状を呈することに加えて、何らかの知的障害を伴うことが多い。疾患そのものは直ちに命を奪うものではないが、水浴びの最中に意識を失って溺死したり、意識のないまま徘徊して行方不明になる患者もいる。てんかん発作への偏見から通学を拒まれたり、知的障害のために教育機会を失う子どもも少なくない。近くの町には国営の診療所があり、抗てんかん薬を無償で受け取ることができるが、薬の種類も職員の知識も限られており、治療を受けても発作が収まらない患者が多い(写真2)。

写真2:現地で用いられる抗てんかん治療薬のパッケージ
私はこれまで、エチオピアでHIV感染症に関する医療人類学調査に従事してきたが(西 2017)、最近になって、うなづき症候群の調査を目的にウガンダ北部を訪れるようになった。村で私の相手をしてくれるお父さんも、身内に患者を抱えている。患者の治療に加えて問題なのは、患者を抱えた家族の負担である (Sakai 2015)。患者の危難を未然に防ぎ、生活の質を確保するには日常的な見守りが欠かせないが、患者の家族はそれぞれ、生計のための労働に従事したり、学校に通う時間が必要である。患者の祖母が健在である場合、日常的な世話役を期待されるが、彼女らにもじぶんの人生がある。医療資源が限られたアフリカの農村で、どのように患者とその家族の生活の質を確保するのかを考えることが、私の調査の課題の一つである。
参考文献
Finnström, Sverker. 2008. Living with Bad Surroundings: War, History, and Everyday Moments in Northern Uganda. Duke University Press.
西真如2017「公衆衛生の知識と治療のシチズンシップ――HIV流行下のエチオピア社会を生きる」『文化人類学』81 (4): 651–69.
Sakai, Kikuko. 2015. Patients Who Face Many Difficulties: A Case Study of a Community Based Organization for the Care and Treatment of Nodding Syndrome in Northern Uganda. Presentation at the Minpaku Project Meeting “How Do Biomedicines Shape Life, Sociality and Landscape in Africa?” National Museum of Ethnology, Suita, Japan, September 25–27, 2015.
[海外出張報告] Mbabazi Christine (ジェンダー・セクシュアリティ班)日本 海外出張期間:2017年1月26 日〜 2月9日
“The Use of Ritual in the Reintegration of Female Ex-child Soldiers in Northern Uganda”
Mbabazi Christine
(派遣先国:日本、ケープタウン/海外出張期間:2017年1月26 日〜 2月9日)
My field research area was Gulu district. The places included in the study were; Pece, Lujorongole, Layibi, Vungatira, Coope Municipality, Gulu Ward A. I also went to Amuru district in Northern Uganda where two important rituals were taking place i.e. moyocer and burying of bones (moyomerok). In all these places the phenomenon of ritual was evident and the people knew clearly what ritual is as this thesis unveils. The research assistant and I moved within Gulu municipality conducting interviews and gathering information from different informants. This however, was done after I had introduced myself to the Gulu district authorities. I went to the office of the Resident District Commission from whom I obtained a written document allowing me to proceed with my field study.
I went to the field three times i.e. February 2008, January 2009 and January 2011. Throughout those three field trip experiences I was enthusiastic, expectant and confident that I would obtain the data I needed. I must admit that I also had my fears and anxieties, for example, I wondered what it would be like for my family if I got abducted myself. I also made an extra trip in October 2010 for a dissemination workshop. Anyone doing an ethnographic study knows the joys and tears of field research. In the following section I present my field research experiences.
In the company of my research assistant I visited the Gulu support the children organization, Layibi sub-ward, Bardege A, and Coope Camp. I obtained valuable information orally through interviews and through observation. All through that time I encountered formerly recruited girls who had served as soldiers in different capacities. I saw their living conditions and carefully listened to their experiences of rituals which they had performed. Hearing and seeing these young girls share their stories of life in captivity was an eye opener to me, who had not been very close to the reality of the conflict in Northern Uganda.
In January 2009, I made another trip to Gulu district. This was for purposes of filling in the gaps which had been identified during data analysis. This second field study trip was very informative and served the purpose of clarity. It was on the 23rd January 2009 that I visited Amuru district a Pabwo village where I witnessed the burial of bones and moyo cer, the ritual of cleansing of the land which were vital in the context of reintegration. Especially, because people were returning to their original homesteads where they had to rebuild and settle once again. By this time I had established connections with the deputy Rwot whom I had interviewed in 2008. We had established a certain degree of trust and so, he called me to go with a team to Amuru, where the rituals were going to take place.

Performing the ritual of Moyo Cer in Pabwo village, Amuru district
In October 2010, I participated in a dissemination workshop in Gulu which formed an important experience of my research process because I presented my findings The participants contributed towards the validation of the findings. My third field research trip took place in January 2011. This served the purpose of concretizing earlier findings and making further clarifications, as well as doing a final observation of the process of reintegration of the formerly abducted girls, with regard to whether rituals played an important role in their lives as they settled down in the community.

Gulu District Administrative Units
[海外出張報告] 小野田 風子(言語・文学班)タンザニア 海外出張期間:2016年9月11日~9月28日、2017年2月24日~3月4日
「スワヒリ文学の受容の場を探る:タンザニアにおける読書環境と読者に関する調査」
小野田 風子
(派遣先国:タンザニア/海外出張期間:2016年9月11日~9月28日、2017年2月24日~3月4日)
私はタンザニア人のスワヒリ語作家の研究を専門に行っており、普段の研究は文献研究が中心になります。しかし文献研究だけでは、どのような人がこの作品を読んでいるのか、作者はどのような人々を読者として想定しているのか、また作品を読んだり議論したりする場はどのようであるのか、ということはわかりません。そこで今回、スワヒリ文学が生み出され、読まれ、議論される場、すなわちスワヒリ文学の受容の場を探るため、タンザニアに赴きました。
調査について述べる前に、タンザニアの文学をめぐる状況を確認しておきます。タンザニアは「スワヒリ語の小説、詩、戯曲の主要な産出国」(Mazrui 2007: 43)と言われています。またスワヒリ語がほぼ100%の人に通じ、識字率は約75%とされています。よって、多数の作家を輩出し、「読める層」も多い国であることがわかります。
一方で、本は高価で、学業修了後は文学作品を手にとって読む機会はほとんどなくなってしまう(竹村 2014)とか、出版社の経済規模も小さく脆弱であるため、作家では生計を立てられない(竹村 1996)といった報告もあり、受容の場としての実態がいまひとつ見えてきませんでした。
今回私が赴いたのは、タンザニアの大都市ダルエスサラームと、その近海に浮かぶ島ザンジバルです。現地では主に三つの内容の調査を行いました。一般人や作家、編集者へのインタビュー、文学学会への参加、そして書店めぐりです。
一般の人々に対するインタビューでは、どれくらい本を買うか・読むか、詩と小説ではどちらがより身近か、など、スワヒリ文学との距離を尋ねるようにしました。その結果、大学生や大卒の人々は研究や教育のための本の他に、小説や自己啓発系の本など幅広い種類の本に触れていましたが、それ以外の人々が買ったり読んだりする本は、子どものための教科書や宗教関係の本、仕事の技術を学ぶための本にとどまり、著名な小説家の名前も知らないようでした。またいずれの人々も読書は現実世界に役に立つ何らかの教えを得るためにすると考えており、純粋に楽しみのために読書をするという習慣はあまり見られないことがわかりました。
一方、スワヒリ詩については異なる結果が得られました。学歴に関係なく、多くの人がスワヒリ語の定型詩を好み、詩の規則について知っていて、詩作や詩の朗唱ができるという人も半数いました。この背景には、テレビやラジオでの詩の番組、大衆歌謡ターラブの歌詞、宗教的な集会での詩の朗唱など、スワヒリ定型詩に触れる機会が多いことが挙げられると思います。同じスワヒリ詩でも、一定の節で歌うことができない自由詩の知名度は低く、口承文芸として受容し得るからこそ、定型詩は大衆性を獲得し得たと言えるでしょう。
詩の大衆性と比べてスワヒリ小説はあまり親しまれていない印象です。そんな中で、複数の大学生が好きな作家として挙げたエリック・シゴンゴ(Eric Shigongo)という小説家については、学歴に関係なく多くの人がその名前を知っていました。彼は小説家かつ自己啓発系の本の著者で、みずから出版社を立ち上げ、自分の作品以外に新聞の発行も手掛けています。さらに講演活動などでテレビにも頻出し、最近は映画の製作にも乗り出したそうです(Reuster-Jahn 2008)。またSNSを駆使したマーケティングを行っており、彼のFacebookページは作品の紹介や講演会の案内などで充実しています。
ページ上には、彼の作品が手に入る書店の名前も挙がっているのですが、今回私はダルエスサラーム市内のそれらの書店を実際にめぐってみました。その結果、11軒の書店の内、彼の作品を確認できたのは7軒、売り切れたと言われたのが1軒でした。これは目当ての本を手に入れることさえ難しいタンザニアにおいては稀有な状態です。シゴンゴの作品は、学校の教材以外の本の中では最も手に入りやすいと言えるでしょう。
シゴンゴの小説の多くは娯楽的な要素の強いサスペンスで、話の展開が早く、ショッキングな内容(性的・暴力的シーン)の連続で、読者を飽きさせない工夫がなされています。実際の売上や、読者層についてはさらなる研究が必要です。しかし彼のようなビジネスマンがスワヒリ語で書いているという事実は、工夫の仕方次第でスワヒリ語の書き物がビジネスとして成り立つことを証明しているようで、スワヒリ文学のさらなる拡大の可能性を感じました。
スワヒリ文学の中には、シゴンゴとは異なり、難解な表現や文学技法を用いた「エリート文学」ともいうべき作品も多く存在します。このような大衆性の低い作品の受容の場はいったいどこにあるのでしょうか。今回の調査で、その答えを垣間見たように思います。それは学会という場です。2016年9月、私はダルエスサラームとザンジバルにおいて、二つのスワヒリ語学会に参加することができました。より大規模であったダルエスサラームの学会では、著名な作家、詩人、政治家などそうそうたる面々が一堂に会し、スワヒリ文学や言語学の成果が情熱的に確認されていました。また新しく出版された小説や詩集の紹介や販売も行われ、多くの人が買い求めていました。二日間の学会で約100人が発表し、その内容はエリート文学からスワヒリ・ポップスの歌詞まで多岐に渡っていました。
学会への参加という経験から、「エリート文学」の受容の場について漠然と気づいたことがあります。それはおそらく大学の文学部を中心とした学生、教員、研究者、卒業生のコミュニティであり、それこそが次世代の作家、詩人、読者、研究者を生み出し続けているということです。エリート文学は、世間一般からは遊離した限定的な知識人のコミュニティの中だけで受容され、規模と質を維持してきたようです。よって消費者数という意味では非常にマイナーではありますが、文学を育んでいこうという熱意は学会などで共有され、再生産されているということが推測できます。
同じことが、作家へのインタビューでも感じられました。今回私は現代スワヒリ文学の重要な作家の一人であるサイド・アフメド・モハメド(Said Ahmed Mohamed)氏にインタビューする機会を得ました。彼の作品の格調高い表現や実験的な構造は、かなり読者を選ぶと思われます。そこで彼に、どのような人を自分の作品の読者として想定しているかと尋ねてみました。すると彼は、隣国のケニアで彼の作品の理解者が一定数いると話し、たとえ自分の作品が難しくて理解できないと批判されても、気にせず書き続けると述べました。この発言からも、特に彼のような難解な作品の受容の場は非常に狭い一方で、その価値を理解し、芸術的質を保とうと努力している層が確実に存在しているということがわかります。ある文化の価値は、その文化の遍在性だけで測れるものではありません。たとえ受容の場は小さくとも、作家の芸術への衝動は普遍的なものであり、彼らの創作活動をこれからも追っていきたいと思っています。
今回の調査は短期間で小規模なものでしたが、スワヒリ文学の多層性をうかがい知ることができました。今後も文献研究とともに現地調査を続け、その受容の場の輪郭をより明確にする必要があります。
参考文献
竹村景子(1996)「民族語文学と出版事情:ケニア、タンザニアの現状を考察する」『アフリカレポート』第23号, アジア経済研究所, 22-25.
竹村景子(2014)「タンザニア:二つの言語の狭間で」『カスチョール』第32号, カスチョールの会, 29-32.
Mazrui, Alamin(2007)Swahili beyond the Boundaries: Literature, Language, and Identity. Ohio University Press.
Reuster-Jahn, Uta(2008)Newspaper Serials in Tanzania: The Case of Eric Shigongo (with an Interview). Swahili Forum 15. pp. 25-50.

新聞、絵葉書、文房具など雑多な商品を置いているザンジバルの書店。

ザンジバルの道端の古本屋。イスラーム関係の本が多く並んでいる。

ダルエスサラームの書店内に並ぶエリック・シゴンゴの本。

ダルエスサラーム大学で2016年9月に開催されたスワヒリ語学会の様子。